Current Exhibition
Ryogoku

“Let's Pink! 6”
Curated by Satoshi Osada
Fumiaki Akahane|Satoshi Osada|Ayano Kaeba|Daichi Sato|Erika Yamashiro|Osamu Watanabe
January 17 (Sat) - February 14 (Sat), 2026
Open: Tuesday - Saturday 11 am - 7 pm
Closed on Sunday, Monday, and National holidays
cooperation: CAVE-AYUMI GALLERY
GALLERY MoMo Ryogoku is pleased to present “Let’s Pink! 6”, a group exhibition curated and organized by artist Satoshi Osada, on view from Saturday, January 17 to Saturday, February 14, 2026.
This exhibition is the sixth installment of a series themed around the color pink, previously held three times in Tokyo between 2009 and 2010, and twice in Okinawa in 2014 and 2024. Marking the first Tokyo edition in sixteen years, this iteration brings together six artists who each explore the diverse expressions and renewed possibilities embodied by the color pink.
Osada approaches pink not merely as a symbol of cuteness, but as a color capable of gently enveloping people and the world, at times carrying a sense of festivity or spirituality. The series has continued as a platform for artists to engage with pink in their own ways and to present unique worlds that emerge from that dialogue.
We invite you to experience the varied interpretations of pink brought forth by each participating artist.
“Let’s Pink!” is an exhibition that was held three times in Tokyo between 2009 and 2010, and for the fourth and fifth times in 2014 and 2024 at Gallery Lafayette in Okinawa.
This exhibition adopts “pink” as its theme color, consciously engaging with expressions that use “pink” and attempting to draw out the color’s abundant charm. Participating artists share the theme of “pink” and explore new possibilities inherent in this color. Pink is said to have healing effects, to promote the secretion of female hormones, and to create a sense of calm, but beyond these effects, the color can present many different expressions depending on how it is expressed and perceived.
There are moments when one may feel enveloped by the depth of “pink,” and moments when one may be surprised by unexpected qualities of the color.
This sixth edition will be held in Tokyo for the first time in 16 years, since the third exhibition.
The participating artists are six in total: three based in the Kanto region and Nagano—Fumiaki Akabane, Ayano Kaeba, and Osamu Watanabe—and three based in Okinawa—Satoshi Osada, Daichi Sato, and Erika Yamashiro. I would like to highlight Akabane and Sato, who are participating for the first time.
Akabane focuses primarily on painting, yet in recent years has developed works incorporating materials such as sand, hemp fiber, beeswax, and substances reminiscent of “soil.” His solo exhibition Rotten Symphony features “anthropomorphized plants and fungi,” and is described as depicting a world that contains the fundamental desires and contradictions of human beings. For him, the “human body” and “living beings” are not isolated individuals but parts of a system connected to forests, soil, fungi, and microorganisms—a relationship he seeks to visualize through painting.
Sato is based in Okinawa, yet possesses a global perspective. In his paintings, characters quietly engage in conversation or appear as though performing music, creating scenes in which “the blink of time” and “stories within the margins” can be felt despite the still imagery. By adding extraordinary elements to seemingly ordinary scenery and motifs, he generates a “coexistence of déjà vu and unfamiliarity.” When classical pictorial elements such as composition, allegory, and narrative overlap with images shaped by the pop and internet age, a sense of “displacement” emerges—an experience that reveals the depth of his work.
A shared characteristic of Akabane’s and Sato’s works is the way motifs or elements that appear contradictory become connected or overlap. Through these connections and overlaps, viewers standing before their works may feel as if they have entered into the paintings themselves—experiencing the unreal world vividly, as though becoming inhabitants of it. In a contemporary era where connection and overlap among people, objects, and events are growing increasingly tenuous, their works remind us of the importance of such relationships. By exhibiting Akabane’s and Sato’s “pink” works together in the same gallery, we hope that their works will connect and overlap with one another as well, offering viewers the chance to experience new charms and expressions of “pink.”
Additionally, all six artists—including Kaeba, Yamashiro, Watanabe, and Osada—share a common characteristic: their range of expression exceeds any single medium or genre.
As the organizer, I (Osada) moved from Tokyo, where I had lived for 13 years, to Okinawa in 2013. In Okinawa—a new home with a warm climate, warm people, and generous inclusiveness—I have sought new possibilities as an artist. Coincidentally, this pursuit overlaps with the concept of “Let’s Pink!”, which seeks new possibilities in the color “pink,” a color that envelops and fascinates people. While the fifth exhibition was held in Okinawa in 2024, ten years after the previous edition, I feel great joy and purpose in presenting the sixth edition in Tokyo, where the works of Okinawa-based artists can be introduced alongside those of artists from other regions.
Satoshi Osada, Organizer of “Let’s Pink!”
Fumiaki Akahane
©2025 Fumiaki Akahane
Photo Go Itami, Courtesy of CAVE-AYUMI GALLERY
Akahane, who seeks to affirm life through painting, has long depicted worlds in which the overwhelming energy of diverse organisms becomes a motif, and in which human beings’ fundamental desires and contradictions are embedded. The anthropomorphized plants and fungi speak to the viewer with a sense of familiarity, while the organically swelling paint textures and colors reveal expressions that are dynamic yet raw and delicate—evoking living entities that are continuously reborn through small, interconnected chains.
Akahane describes his own process as “gathering paint like a dung beetle and being led by the paint as I work.” His works allow viewers not only to encounter the motifs themselves but also to glimpse his process: entering into the painting, manipulating the paint as it shifts, and creating as though immersed within the work.
1984 Born in Nagano Prefecture, Japan
2008 Graduated from Musashino Art University, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting
Current Based in Nagano Prefecture, Japan
Selected Solo Exhibitions
2024 Life and Circulation, Anformel Nakagawa Museum of Art, Nagano
2023 Soil Psychedelia, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo
2023 SOILS AND SURVIVORS, Suwa City Museum of Art, Nagano
2022 Rotten Symphony, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo
2020 Against gravity, Token Art Center, Tokyo
2019 Compost Paintings, Art Lab Hashimoto, Kanagawa
2017 OILY YOUTH, Musashino Art University gFAL, Tokyo
2015 OK PAINTING, One’s Room Gallery & Studio, Okinawa
Selected Group Exhibitions
2023 ART SANPO 2023, Various Stores, Imabari, Ehime (Curated by Imabari Landscapes)
2023 VOCA 2023: Perspectives of Contemporary Art – New Flat-Plane Artists, Ueno Royal Museum, Tokyo
2021 Fumiaki Akabane & Taichi Nakamura, PAINTINGS, CAVE-AYUMI GALLERY, Tokyo
2020 National Okutamako – Mochitsumo Taretsu Okutama Coin, gallery αM, Tokyo
2017 Spring Fever, Komagome Warehouse, Tokyo
2016 Takato KONJAKU STORY, Shinshu Takato Art Museum, Nagano
2015 Fumiaki Akabane & Keiri Koizumi, Two-Person Exhibition, TS4312, Tokyo
2012 The Power of a Single Painting, NADiff a/p/a/r/t, Tokyo & Hiyori Art Center, Ishinomaki
Awards
2024 Izumi Kato Prize x Fundación Casa Wabi 2024–2025
2008 Excellence Award, Musashino Art University Graduation Exhibition
2007 Selected, WONDER SEEDS 2007

Satoshi Osada
©Satoshi Osada
Photo:Yutaka Nozawa
The themes of my work include transience, frailty, ambiguity, lightness, wistfulness, loneliness, delicacy, and a sense of insufficiency. These qualities can be considered characteristic aspects of Japanese sensibility and emotion. Through lightly applied colored pencil, fine and slender lines, and dripping techniques, I express elements such as transience, fragility, wistfulness, and delicacy.
The series of “lightly drawn colored-pencil works” began with an experimental drawing created around 2009. Since resuming this approach around 2020, several new bodies of work have gradually emerged—such as collages incorporating cut pieces of newspaper onto the drawing, adding handwritten waka poems, and painting on clay surfaces.
1980 Born in Shizuoka Prefecture, Japan; based in Okinawa Prefecture since 2013
2004 Graduated from Kokugakuin University, Faculty of Letters, Department of Philosophy
Selected Solo Exhibitions
2023 HARMONY/MASHUP/NEUTRAL, Gallery Atos, Okinawa
2021 TIME LEAP WORKS, Yorokobi to Gallery, Tokyo
2019 NEW DAWN AFTER CHAOS, Museum Shop, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, Okinawa
2013 Microcosmos Superposed, GALLERY MoMo Projects, Tokyo
2009 Microcosmic Chaos, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii, Tokyo
Selected Group Exhibitions
2025 Satoshi Osada & Erika Yamashiro, HARMONY POLYPHONY, Gallery Atos, Okinawa
2025 Make It Visible – Complete & Incomplete, HANSOTO, Shizuoka (Curated by Satoshi Osada)
2024 The Current State of Drawing, Moro Production Studio, Saitama (Curated by Kouta Hirakawa)
2024 Let’s Pink! 5, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)
2017 Tetsu Osada & Kouta Hirakawa, Scenes of the Intermediary, Gallery Atos, Okinawa
2015 Nise the Choice, Billiken Gallery, Tokyo (Curated by Hiroyuki Nisouki & Yuki Kudo)
2011 Tetsu Osada & Daichi Aijima, Make It Visible 4, DOROTHY VACANCE, Tokyo
2010 Tetsu Osada & Ichiro Jaga, Klee Exhibition – Post Klee, Higashinakano Tohoichi, Tokyo
Selected Performances
2022 NERD ART BOOK SHOP, NERD GALLERY, Okinawa
2010 Let’s Pink! 3, WOMB LOUNGE, Tokyo
2009 NEXT DOOR MIX EXHIBITION, T&G ARTS TOKYO, Tokyo
Awards
2019 Selected, The Choice × merlot
2007 Selected, WONDER SEEDS 2007
2006 Selected, 26th Graphic Art Hitotsubo Exhibition
2003 GEISAI #3, Tomio Koyama Gallery Award

Ayano Kaeba
©Ayano Kaeba
I create paintings on supports of various shapes—such as cut plywood, canvas, and paper—interweaving contemporary and personal narratives while incorporating textiles and classical patterns.
When I touch a cold fence,
I am reminded of the things woven within myself.
Even as I wish to release the chains that feel like a curse,
they sometimes soothe me, gently leaning close.
Entangled with memory and everyday life,
these soft chains shift their form like living creatures,
holding within them the colors of my inner world.
1984 Born in Kanagawa Prefecture, Japan; currently based in Saitama Prefecture, Japan
2008 Graduated from Tama Art University, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting
Solo Exhibitions
2012 GALLERY MoMo Roppongi, Tokyo
2009 GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo
Group Exhibitions
2025 Threads of Resonance: Women Weaving Stories, GALLERY MoMo Roppongi
2024 Let’s Pink! 5, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)
2020 Reflection, GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo
2017 On Paper – Monochrome & Colors, GALLERY MoMo Projects, Tokyo
2014 2 + 2 After Birth, GALLERY MoMo Projects, Tokyo
2014 Let’s Pink! 4, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)
2009 Winter Session of 4 Artists – Spring is Here?, Seibu Shibuya, Tokyo
2009 Let’s Pink!, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii (Curated by Satoshi Osada)
2009 Summer Group Show Hop Step Jump, GALLERY MoMo Roppongi, Tokyo
2008 Opening Exhibition, GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo
2008 ART AWARD TOKYO 2008, Gyoko Underground Gallery, Tokyo
2007 WONDER SEEDS 2007, Tokyo Wonder Site Shibuya, Tokyo
2007 Fore Runners & Four Eggs, GALLERY MoMo, Tokyo

Daichi Sato
©Daichi Sato
Drawing from the influences of classical painters such as Jan van Eyck, Nicolas Poussin, and Édouard Manet, as well as Japanese masters like Tawaraya Sōtatsu, he develops motifs inspired by film and pop music.
In works where lines of dialogue seem to emanate from paintings that should, by nature, be silent, one senses the artist’s wish: that viewers, like himself, may relax, let go of tension, and come to live happily and authentically, true to who they are.
1985 Born in Saitama Prefecture, Japan
2009 Graduated from Okinawa Prefectural University of Arts, Faculty of Fine Arts, Department of Oil Painting
Current Based in Okinawa Prefecture, Japan
Selected Solo Exhibitions
2024 Endless Boundless And Aimless, Cliff Garo Brewery, Okinawa
2024 Ni Estu Amikoj, MJK Gallery, Tokyo
2023 Choose Your Weapon, Hiro Okamato, Tokyo
2021 Meet on the Horizon, OIL by Bijutsu Techo, Tokyo
2017 Eat, Think, and Share Time Alone, Baby Baby HAMBURGER & BOOKS, Okinawa
2016 Planedo, Tomari, Okinawa
2015 Good Paintings, One’s Room Gallery & Studio, Okinawa
2011 Repair, M&A Gallery, Okinawa
Selected Group Exhibitions
2019 Paradiso, Moon Beach Hotel Gallery, Okinawa
2019 Untamed vol.2, COHJU Contemporary Art, Kyoto
2018 Metamorphosing Reality, Espai Souvenier, Barcelona
2013 Chain Reaction, Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo
2013 Genetic, Ikei Island, Okinawa
Art Fairs
2024 SWAB, Barcelona
2022 Art Fair Tokyo, Tokyo
2021 Untitled Art Miami Beach, Miami
2021 Art Osaka, Osaka
2020 Art Osaka Wall by APCA, Osaka
2018 SWAB, Barcelona
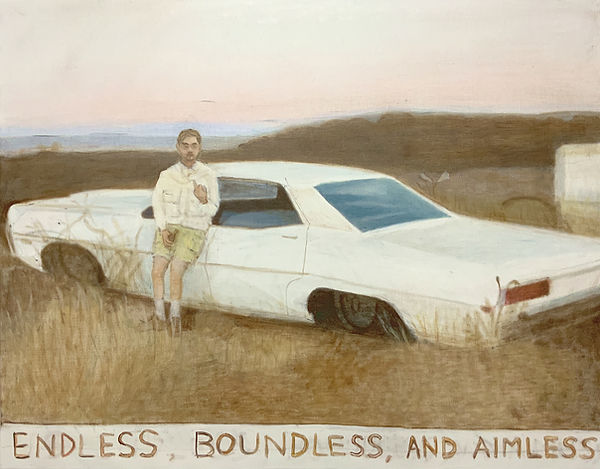
Erika Yamashiro
©Erika Yamashiro
She creates feminine and fantastical worlds with an elegant and decorative touch, weaving a sense of narrative into each work. She has exhibited widely in Tokyo, Okinawa, Los Angeles, Miami, Hong Kong, and other cities.
Her illustrations include numerous book covers for Akutagawa Prize and Naoki Prize-winning authors, and in 2015 she provided artwork for Hitomi Kanehara’s serialized novel in The Asahi Shimbun.
In 2018, her work was featured in the 10th Anniversary Exhibition of the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, with one piece selected for the museum’s premium anniversary ticket. Her work is now part of the museum’s permanent collection.
1979 Born in Okinawa Prefecture, Japan
2002 Graduated from Joshibi Junior College of Art and Design
2005 Graduated from Seto Mode Seminar
Selected Solo Exhibitions
2025 Erika Yamashiro Drawing Exhibition, Museum Shop, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, Okinawa
2021 Cloud Girl Original Illustrations Exhibition, CAMP TALGANIE Artistic Farm, Okinawa
2015 Illustrated Book Exhibition: Storytelling Pictures, Café Unison, Okinawa
2013 striped tail, GALLERY MoMo Projects, Tokyo
2011 erikatica, M&A Gallery, Okinawa
2009 erikatic doll, FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii, Tokyo
Selected Group Exhibitions
2025 Satoshi Osada & Erika Yamashiro, HARMONY POLYPHONY, Gallery Atos, Okinawa
2017 10th Anniversary Exhibition of the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum,
Sea of Encounters – Intersecting Realism, Okinawa Prefectural Museum & Art Museum
2014 Let’s Pink! 4, Gallery Lafayette, Okinawa (Curated by Satoshi Osada)
2013 Pretty Girls, Above Second Gallery, Hong Kong
2012 Hello Spring!, GR2, Los Angeles
2007 WONDER SEEDS 2007, Tokyo Wonder Site Shibuya, Tokyo
2007 28th Graphic Art Hitotsubo Exhibition, Guardian Garden, Tokyo
2007 GEISAI in GIANT ROBOT, Kaikai Kiki presents, GR2, Los Angeles
2006 NADA Art Fair, Kaikai Kiki Booth, Miami
Awards
2007 Selected, WONDER SEEDS 2007
2007 Selected, 28th Graphic Art Hitotsubo Exhibition
2006 GEISAI #10, Bijutsu Techo Prize, Giant Robot Prize, Perfect Attendance Award
2005 GEISAI #7, Casa BRUTUS Prize
2001 Geijutsu Dojo GP, Illustration Editorial Department Scout Award

Osamu Watanabe
©Osamu Watanabe
Recognized as a pioneer who has elevated the techniques of “sweets deco” to the level of art, she has been featured on programs such as Tokyo Kawaii TV (NHK) and Tetsuko no Heya Special (TV Asahi). Her works, crafted with colorful and meticulously detailed creams, candies, and fruits that appear strikingly lifelike, have drawn attention both in Japan and abroad, with solo exhibitions in China, Indonesia, Italy, Belgium, Turkey, the United States, South Korea, and other countries.
In addition to three published art books, her works are held in the collections of nine museums in Japan, including the Ohara Museum of Art and the Kasama Nichido Museum of Art.
The color pink, for her, is not merely a symbol of cuteness; it also illuminates the spirituality of Mexican culture, reflecting rituals of celebration, prayer, and the cyclical passage between life and death. The vivid colors exemplified by architect Luis Barragán are said to arise from Mexico’s embrace of life in its entirety, a bright acceptance of death rather than its denial. Religious decorations such as crosses and hearts covering walls, and the veneration of ancestors symbolized by the Day of the Dead, all convey a faith in the power of color—not mourning, but blessing.
Inspired by this Mexican decorative culture, she has developed a new concept called Ultra Sweets Baroque. Referencing the extravagance of Mexican “Ultra Baroque,” she reconstructs symbolic motifs such as skulls, Madonnas, hearts, and crosses using the textures and materials of sweets. By intersecting this decorative language—often associated with sweetness and lightness—with themes of mortality and prayer, she aims to evoke a sense of “celebratory life” through the vivid power of pink.
1980 Born in Yamaguchi Prefecture, Japan
2003 Graduated from Tokyo Zokei University, Department of Design
Public Collections
Ohara Museum of Art
Kiyosu Haruhi Museum of Art
Shiga Kogen Roman Museum, Yamanouchi Town
Takasaki City Museum of Art
Okazaki World Children’s Art Museum
Hirano Museum of Art
Ohara Children’s Art Museum
Kasama Nichido Museum of Art
Sakata City Museum of Art
Publications
SWEET OR UNSWEET?, BNN Shinsha
OSAMU WATANABE POSTCARD BOOK, Parco Publishing
Osamu Watanabe Sweets Deco Method, Seibundo Shinkosha




